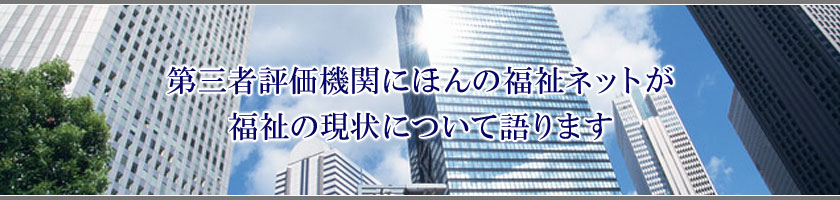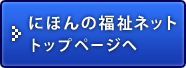最新情報
- 05月19日・・・評価受審、その後
- 05月12日・・・井上さく子先生
- 05月12日・・・佐藤ちよみさん
- 09月12日・・・絶賛活動中です。
- 12月01日・・・ode an die freude/ ode to joy/ 歓喜の歌
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申上げます。
頻繁な情報の発信、ホームページの更新がままならない状況が続いておりますが、社員一同、馬車馬のように走り続けております。
年度末まであとわずかではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
㈱にほんの福祉ネット
2012年01月05日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 近況
人が発する言葉、言葉が語る意識
(1) 破壊された街を復旧させていると、ダメージを受ける以前の(元の)自分自身を回復しているかのように感じる。
(2) ただ元に戻す復旧ではなく、創造的な復興案を示してほしい。
さて、それぞれ、どのような立場の人が発した言葉でしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)は、ハリケーン・カトリーナにより打撃を受けたニューオリンズのある被災者の言葉。
(2)は、ある被災地の復興策をめぐる某国首相の言葉。
(2)は、ノーベル経済学賞(俗称)を受賞したある経済学者の次のような言葉と重なります。
ニューオリンズ市内の学校の壊滅的な状況を念頭に置いて曰く、
(3)これは悲劇である。そしてまた、教育システムを根本的に変えるための、またとないチャンスでもある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)と(3)は、カナダのジャーナリストであるナオミ・クラインによる“The Shock Doctrine”の序章“Blank is beautiful”(まっさらな紙は美しい)で紹介されている言葉です。
(1)は、失われた暮らし-住み慣れた街、関わりのあった人、思い出、その他諸々の人としての営み、その積み重ねなど-が、人にとってどれほど大切なものであったのかを物語ります。
(2)は、さて何なんでしょうか? 困りました。ネット上で“拾った”言葉らしく、なんとも軽く、また薄い。そしてその実、恐ろしく残酷な言葉です。
「ただ元に戻す復旧ではなく」「創造的な復興案」、、、人にとっての故郷や失われたものの意味、失った人の気持ち、そんなもんは知らん、さーて新しい街でも作るぞ!-こんなところでしょうか。
(3)は凄いですね。実はこういう輩、某国の政治家・大学教授などにも時々います。(2)のような言葉を発する人間のブレーン(と言って本当に良いのか?)である場合もあります。
このように見ると、言葉はとても正直に自己を語ります。自分の言葉にも自分自身が表れているかと思うと、しばし考え込んでしまう今日この頃です。
2011年07月29日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 近況
美しき旋律
心身に染み渡ります。そう、Jaki Byard の奏でるメロディー。
ちなみに、昨年発売された大西順子のアルバムには、氏に捧げた曲が収録されています。
2011年07月21日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 未分類
切る言葉、つなげる言葉
とある若き評価者とのお酒の席でのお話。当時の彼は、高齢者施設に勤務。
お酒もすすみ、ついつい追加オーダーする私。
私:「○○2つ下さい」
店員さん:「すみません、あと一つしかないんです」
ここで、注文を止める場合、皆さんならどのように返しますか?
ちなみに、その時の私の返答。
「じゃ、いいです」
間髪いれず、若き評価者曰く、
「次来た時に楽しみにしてます」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同じ事柄であっても、捉え方や表現には様々なものがあります。
そして、様々なものがあるのであれば、より良いものを選びたいものです。
さらに望むべくは、それを意識しなくとも出来るようになることですが。
「じゃ、いいです」と(そのつもりがなくても)断ち切るような表現では、関係はそこで終わり。発展の可能性は消えてしまいます。
これに対し、「次来た時に楽しみにしてます」との表現では、相手との間に、次につながり得るポジティブな心の循環が生まれます。
豊かな言葉の使い手(=豊かな心の持ち主)のまわりには、当然のことながら、豊かな人間関係があります。
2011年05月09日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 近況
平成23年度 福祉サービス第三者評価受審のお申込みについて
新年度に入り、はやひと月が過ぎようとしています。
昨年度中は、60を超える事業者様と、評価(準ずる調査含む)を通じて関わりを持たせて頂くことが出来ました。
事業者の皆様には、改めて御礼申し上げます。
皆様から頂戴した様々なお声などを糧に、今後とも評価のさらなる質的向上に努めて参ります。
さて、当社では、平成23年度の福祉サービス第三者評価受審のお申し込みを受付中です。
評価の正式なご依頼の有無に関わらず、評価そのものについてのご質問やお見積書の作成・提出など、評価に関わることであればどんな事でもお問い合わせ頂いて結構でございます。
今年度も、多くの事業者様と関わりを持たせて頂けることを楽しみにしております。
2011年04月26日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 営業
支援―やる気を漲らせる都内施設
震災の発生から、はや2週間が経過しました。
被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
被災地の現状が明らかになるにつれ、いたたまれない思いにかられます。
そんな中、福祉の現場では、現地への職員の派遣、被災者の受け入れなどに、積極的な姿勢を見せる方々がいます。
以下は、神戸で被災した経験をお持ちの都内特養の施設長様からうかがったお話です。
・神戸が震災に見舞われた際、特に支援に熱心だったのが、浅野史郎知事(当事)率いる宮城県だった。宮城が窮状に陥った現在、神戸の方々が“燃えている”。同じく、被災した新潟の方々も。
・施設職員には、東北出身者もいる。被災地への介護職員の派遣については、多くの職員が手を挙げている(すでにメンバーは選定済み)。
・施設長のところは、ショートステイやデイサービスを併設する、いわゆる複合施設。曰く、「いざとなれば、併設の在宅サービスの営業を休止してでも、被災者を受け入れる」。当然、現在の利用者に対するフォローも行なうのが前提。
・また、さらに曰く、「近隣の団地に支援が必要な被災者が滞在することになれば、職員を派遣する」。その際には、都内のヘルパー経験者の方々の力が必要になることも。
お話し頂く際の施設長様の表情は、冷静な中にもやる気を漲らせていました。また、非常に前向きでした。
「出来るか出来ないか」を論じるのではなく、「やるかやらないか」の決断で動く―施設長様のお話は、聞く者をも前向きにさせます。
施設を舞台とした支援が展開される際には、微力ながら協力させて頂きたいと思います。
2011年03月28日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
統合失調症の最新情報
東京都精神医学総合研究所では、今年度、「統合失調症の最新情報 予防、治療、研究の新しい流れ」をテーマに、都民講座を開催しています。ちなみに第1回講座はすでに申込を締め切っています。主催者によれば、応募者多数のため、抽選となったとのこと。世間一般でのこの分野への関心の高さをうかがわせます。
以下、年間スケジュールを転載します。
第1回 平成22年6月22日(火)
オーバーヴュー;統合失調症の最新情報
東京都立松沢病院院長 岡崎 祐士
申込期限:6月8日(火)消印有効 すでに締め切り
○現在受付中
第2回 平成22年7月21日(水曜日)
統合失調症の治療-薬物療法とリハビリテーションの深いつながり-
東京女子医科大学医学部精神医学教室 教授 石郷岡純
申込期限:7月7日(水曜日)消印有効
○これからの予定
第3回 平成22年9月7日(火曜日)
精神病性疾患の早期介入-疫学的知見を踏まえて-
東京都精神医学総合研究所 研究員 西田淳志
申込期限:8月24日(火曜日)消印有効
第4回 平成22年10月13日(水曜日)
統合失調症の病態と治療-脳画像検査でわかったこと-
日本医科大学精神医学教室 教授 大久保善朗
申込期限:9月29日(水曜日)消印有効
第5回 平成22年12月8日(水曜日)
脳科学研究から見えてきた統合失調症の原因と治療
東京都精神医学総合研究所 研究員 糸川昌成
申込期限:11月24日(水曜日)消印有効
○開始時間・場所などは、各回とも共通です。
講演時間:午後2時~3時30分(午後1時開場)
会場:津田ホール(JR中央線・千駄ヶ谷駅前)
定員:490名(事前申込制・抽選) 入場無料
○申込先
〒156-8585 東京都世田谷区上北沢2-1-8
東京都精神医学総合研究所 調査係 宛
※お名前と「第○回都民講座(○月○日)」と明記のうえ、往復ハガキにてお申込みください。(1名様につき1枚) 記入方法はこちら。
○問い合わせ先
東京都精神医学総合研究所 調査係 電話 03-3304-5738
主催:財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所
協賛:都立中部総合精神保健福祉センター/都立松沢病院
以上、http://www.prit.go.jp/Ja/Outline/tomin.html およびhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2010/06/22k6e301.htmより転載。
2010年06月18日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 情報提供
杉並区立16保育園の評価結果
当社が担当させて頂いた平成21年度の杉並区立16保育園の評価結果が、区のホームページ上でまとまった形で公開されています。総ページ数623、前半が保護者アンケートの分析、後半が評価結果報告書という構成です。ご関心をお持ちの方は、リンク先をご覧下さい。
2010年05月20日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 事務連絡
理念、理念、理念~「良き何か」に向かうということ
ちょっと感動を覚えてしまったので、某国の新首相の会見を抜粋します(非常にクリアな英語です)。
連立を組むことになった経緯を述べた後、次のように述べます。
2:08~
“I believe that is the right way to provide this country with the strong, stable, good and decent government that I think we need so badly.”
「これ(=連立を組むこと)こそが、我々が本当に必要とする政府―強く、安定的で、良き、真っ当な政府―をこの国にもたらすための、正しい方法なのです。」
さらに演説は続きます。
2:19~
“Nick Clegg and I are both political leaders who want to put aside party differences, and work hard for the common good and for the national interest. I believe that is the best way to get the strong government we need, dicisive government we need today.”
「(連立を組む)政党間の相違はひとまずわきにおき、共通善と国益のために頑張りたい―(保守党党首の)ニックと私とは、ともにそのように考える政治家です。これが、我々に必要な強い政府、今必要な決定力のある政府を作る最善の方法なのです。」
ここには、進むべき方向性が不明瞭なスローガンは出てきません。あるのは、goodであり、decentであり、the common goodです。
より良いもの、崇高なものに向かうこと―このことこそが、個人であれ、人の集団である組織であれ、健全でありうる、あるいは、少しでも真っ当でありうるための源泉なのかもしれません。この意味で、昨年度関わりを持たせて頂いたとある認証保育所は、誠に誠に良い例でした。
「○愛」、「反○○」、「○新」・・・、理念の出番なき劇というものは、役者を醜くしてしまうもののようです。
goodや、decent、the common goodといった言葉がなんの躊躇もなく、澱みもなく出てくること。
どんなに荒廃した時代でも、健全な精神はこんなところで顔を見せてくれます。
なんだか救われた思いがすると同時に、彼の国をうらやましくも思う今日この頃です。
※“decent(ディーセント)”とは、語源的には “decet=fitting=ぴったりの、適当な、ふさわしい”であり、第一義的には「きちんとした」の意。では、何を基準に判断して「きちんと」しているのかといえば、decentが「道徳にかなった」との意味も持つことを考え合わせると、「価値の体系としての常識(良識)を基に判断すると、きちんとしている」ということだと解釈できます。
2010年05月20日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 近況
新年度を控え、改めて評価に対する姿勢について
「福祉の現状について語る」と大見得を切っておきながら、長らく開店休業中のブログですみません。
さて、当社の現状ですが、おかげさまで、すべての案件が(ほぼ)終了いたしました。今年度も、評価事業を通じて多くの素晴らしい事業者様とのご縁を頂きました。継続的なご依頼、事業者様によるご紹介、自治体の入札を含め、ご依頼頂いた事業者様の数は52にのぼります。本当にありがとうございました。
今年度の山場は、○○区の認可保育園16園の評価でした。幸いなことに、どの園長先生からも、概ね、「実情を正確に捉えて頂いた」とのお言葉を頂戴しました。また、主管課の○長からは、「毎年、評価者に関するクレームが多数寄せられますが、今回はゼロでした(笑顔)」とのお言葉を賜りました。本当にありがたい限りです。
ここで、改めまして、当社の姿勢・方針を申し上げます。
当社は、福祉施設の利用者と事業者をつなぐメディアとして、業務の改善や質の向上の触媒として、「第三者評価」の活動を行っています。
あくまでもメディアです。事業者の上に立って「あーだこーだ」言うものではありません。つまり、手法に着目すれば、評価とは本質的には「インタビュー」です。
また、インタビューでは、これまでの取り組みの蓄積としての現在をもとにしつつ、今後向かうべき将来についてお聞きしています。この意味で、評価とは「プラスのアセスメント」です。
いずれにいたしましても、評価とは、コミュニケーションの一類型です。
では、評価というコミュニケーションで大切な点とはなんでしょうか。
これは、「経営的な視点が大切なんですよ~」とご高説を垂れる大変ご立派な見識をお持ちの経営コンサルタントのオジサマ集団には致命的に欠けている点です。
ある学者は、ワーグナーのオペラ『パルジファル』を例に言います。
・・・・もの知らずのパルジファルが漁夫王に向かって適切な質問をしなかったことから、王国の荒廃がはじまっている。適切な質問はコミュニケーションを生む。荒廃はコミュニケーションの疎外をきっかけとして、人の心の世界に拡がっていくのだ(。)
中沢新一(2009年)『緑の資本論』ちくま学芸文庫 pp.32-33
当社にも、高齢者の介護や障害者の支援、子どもの保育などの分野で経験を積んだ評価者が多数おります。この貴重な経験に基づく専門的な知識は、評価においては、聞く姿勢があってこそ活きてきます。
当社は今後とも、事業者様の、「これまでの取り組みの蓄積としての現状」や「将来への積極性としての課題」などを可能な限り正確に把握し、表現し、伝達するメディアとしての役割を果たすべく、真摯に取り組んでまいります。
2010年03月24日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |